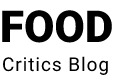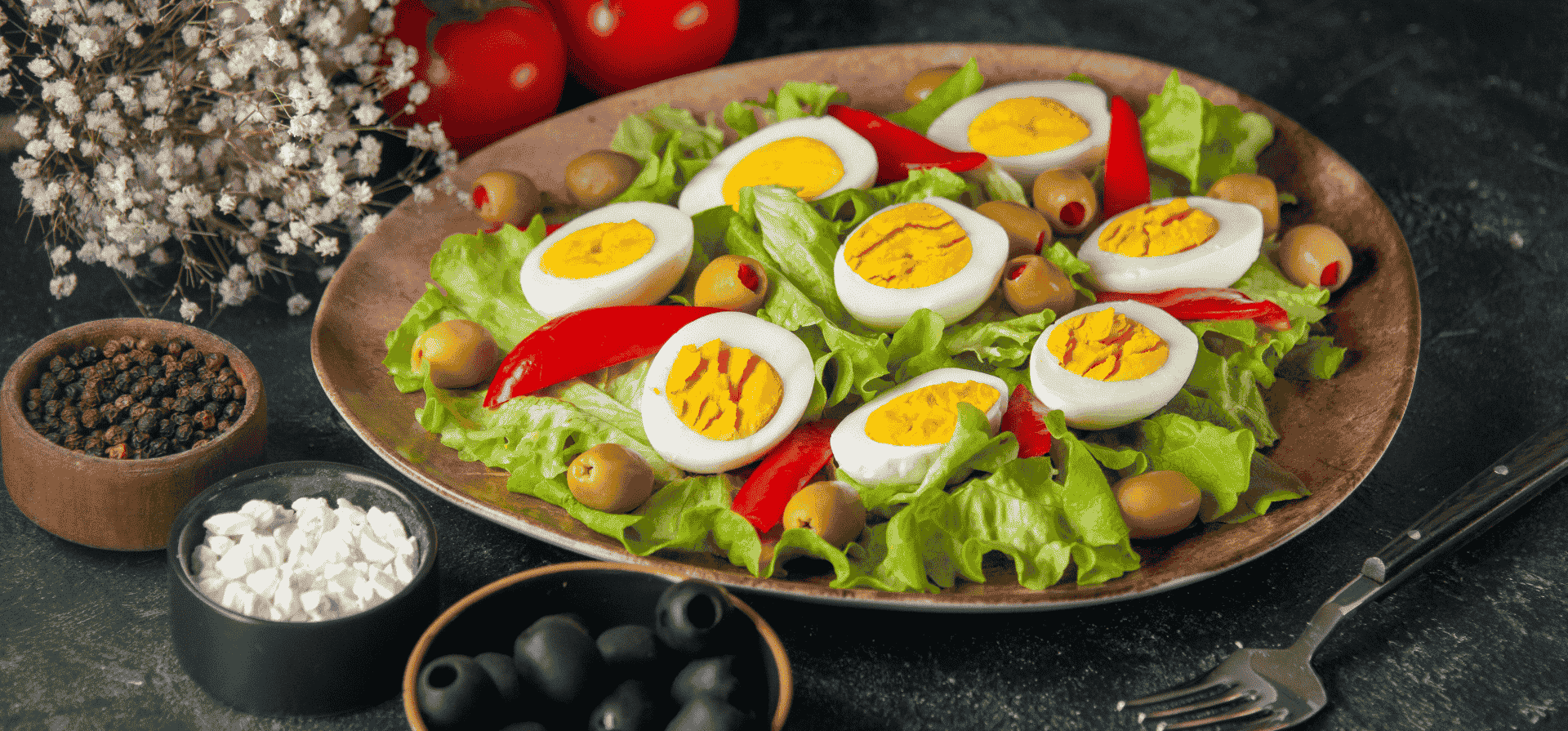もちもち食感!アワビの肝を使った滋養たっぷりのお粥
元気回復に最適!栄養満点アワビの肝粥の黄金レシピ

体に良いとされるアワビの肝をたっぷり使った、濃厚な旨味と栄養が詰まった滋養粥です。長引く風邪で薬を服用し、胃腸の調子を崩しがちな自分と子供たちのための、まさにスタミナ満点のお粥。元気を取り戻すための、満足感のある一品をぜひお試しください!
お粥の材料- もち米 500g
- 下処理済みのあわびの肝 300g
- 水 2L(または、あごだし昆布だしなどの出汁)
調味料・トッピング- エゴマ油(またはごま油)大さじ3
- 料理酒(または生姜酒)大さじ2
- 醤油または塩(味調整用)
- いかなご醤油(ナンプラー)大さじ1(お好みで、旨味アップ)
- こしょう 少々
- 白ごま 大さじ5(細かくすりつぶしたもの)
- エゴマ油(またはごま油)大さじ3
- 料理酒(または生姜酒)大さじ2
- 醤油または塩(味調整用)
- いかなご醤油(ナンプラー)大さじ1(お好みで、旨味アップ)
- こしょう 少々
- 白ごま 大さじ5(細かくすりつぶしたもの)
調理手順
Step 1
まず、もち米500gを流水で数回丁寧に洗い、水が澄むまで洗ってください。洗ったもち米はボウルに入れ、30分間しっかりと浸水させます。こうすることで、お米がより柔らかくなり、煮崩れしやすくなり、美味しいお粥が作れます。

Step 2
下処理済みのあわびの肝300gは、約0.5cm角の細かさに刻んで準備します。肝の見た目が気になる場合や、お子さんが食べやすいようにしたい場合は、フードプロセッサーや包丁で非常に細かく刻んでいただいても構いません。こうすることで、肝の風味が粥全体に均一に広がり、風味を楽しめます。

Step 3
いよいよお粥を炒める工程です。鍋にもち米ともち米を刻んだあわびの肝を入れ、エゴマ油(またはごま油)大さじ3を回しかけ、中強火で約3分間炒めます。お米が半透明になり始めたら、料理酒(または生姜酒)大さじ2を加え、さらに1〜2分炒めます。この過程で、あわびの肝の生臭さを取り除き、風味を豊かにします。

Step 4
炒めたもち米とあわびの肝に、冷たい水2L(または、あらかじめ準備しておいたあごだし昆布だしなどの出汁)を注ぎ入れます。お粥を煮る際は、最初からたっぷりの水分を入れておくことで、煮詰まりすぎるのを防ぎ、滑らかな食感を保つことができます。

Step 5
強火で沸騰させ始めたら、お粥の表面にアクが出てきます。このアクを、お玉などを使って丁寧にすくい取ってください。アクを取り除くことで、お粥がよりすっきりと滑らかになります。アクを取り除いたら火を中弱火に落とし、鍋底が焦げ付かないように、ヘラで頻繁にかき混ぜながら、じっくりと煮込んでください。

Step 6
あわびの肝自体にある程度の塩分が含まれているため、お粥がほぼ完成した頃に味を調えるのがおすすめです。まず、こしょう少々を加えて風味をプラスします。私は別で出汁を取らなかったため、旨味をプラスするためにいかなご醤油(ナンプラー)大さじ1を加えました。お好みで、醤油や塩を使って味を調整してください。

Step 7
もち米のお米粒が十分に煮崩れ、お粥の濃度がちょうど良くなったら、最後に白ごま5大さじを準備します。白ごまは、ごみを取り除き、キッチンペーパーなどでこすってきれいにした後、細かくすり鉢ですりつぶします。すりつぶした白ごまを、お粥の上にたっぷりと散らしてください。こうすることで、香ばしい風味が増し、食感も加わり、より美味しくいただけます。

Step 8
昔から、あわびの肝はあわびの身よりも栄養価が高いと言われています。このように栄養満点な、あわびの肝粥が完成しました!香ばしい匂いのせいか、最初は粥の色が気に入らないと言っていた子供たちも、あっという間に一膳平らげてくれました。皆様も、この美味しい滋養粥で元気を取り戻してくださいね!