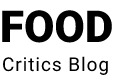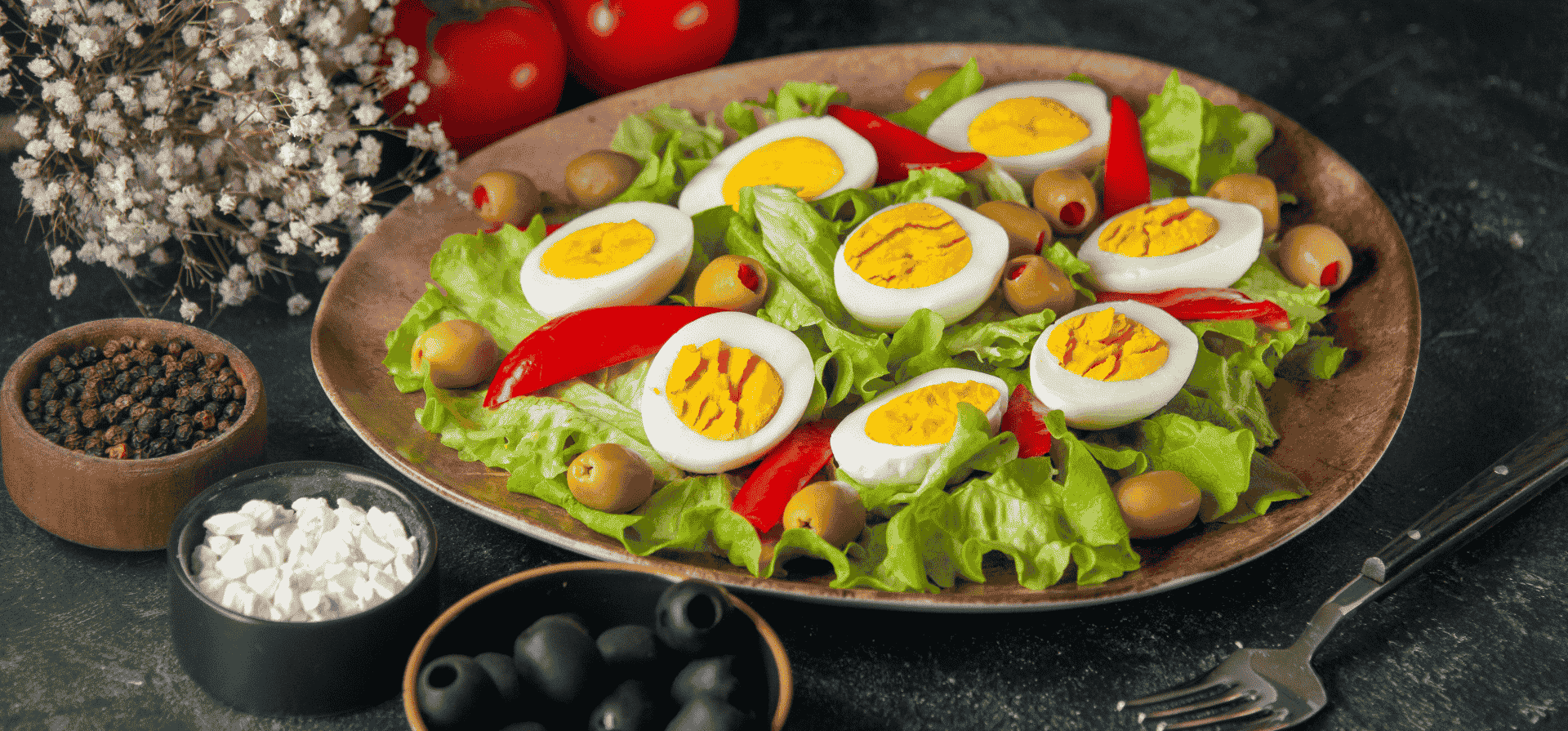本格もち米の薬飯(ヤッパ)
炊飯器で簡単!伝統的な薬飯(ヤッパ)の作り方

お祝い事や特別な日、または満足感のある軽食が食べたい時のために、最高の選択肢です!炊飯器ひとつで簡単に作れる、もちもちで美味しい薬飯(ヤッパ)のレシピをご紹介します。繊細な甘さと香ばしい風味が特徴で、たっぷりのナッツが食感を豊かにしています。特別な日には、心を込めて手作りした薬飯を大切な人にプレゼントしましょう。
材料 (計量:一般的な紙カップ | 大さじ)- もち米 4カップ(洗って30分浸水させたもの)
- デーツで抽出した水 3カップ
- 黒糖 2/3カップ(黄砂糖で代用可)
- 濃口醤油 1/2カップ
- ごま油 大さじ5
- シナモンパウダー 大さじ2(オプション)
- ナッツ類(お好みで)
調理手順
Step 1
まず、もち米4カップをきれいに洗い、30分間水に浸しておきます。これは、薬飯特有のもちもちとした食感を引き出すための重要な工程です。薬飯の甘くてしょっぱい味の決め手となるタレを準備しましょう!デーツで抽出した水3カップに、黒糖2/3カップ(甘さは好みで調整し、黒糖がない場合は黄砂糖でも代用できます)、濃口醤油1/2カップ、そして香ばしさを加えるごま油大さじ5杯を加えてください。シナモンの香りがお好みであれば、大さじ2杯程度加えてください。我が家では、シナモンの香りをあまり楽しまず、子供たちが嫌がることもあるため、省略することもよくあります。ナッツ類は、お好みに合わせて準備してください。私は故郷で採れた栗とデーツ、そして母が自家製で乾燥させた干し柿を使用しました。栗、デーツ、干し柿の他に、くるみ、松の実、ひまわりの種など、お好きなナッツを自由に入れてみてください。

Step 2
もち米はあらかじめ浸水させておき、甘くてしょっぱいタレも事前に作っておきました。タレをあらかじめ作って少し味見をすることで、自分が望む甘さと塩味のバランスを調整できます。もし味が薄ければ、砂糖や醤油を少し加えて味を調えてください。私は薬飯がとても好きなので、何度も作ってきたので、もうこの量ならあっという間に作れます。皆さんも何度か作ってみると、すぐに慣れるでしょう。

Step 3
準備したタレにもち米ともち米に混ぜる具材(ナッツ、デーツ、干し柿など)をすべて加え、均一に混ぜ合わせます。米粒ひとつひとつにタレが均等に絡むように、優しく混ぜ合わせることが重要です。

Step 4
さて、炊飯器にもち米とタレを混ぜたものを入れ、炊飯する番です。もち米を浸水させていない場合は、もち米がかぶるかかぶらないかくらいの量のタレを加えてください。しかし、今回はもち米をあらかじめ浸水させているので、タレがもち米の表面から少しだけ見える程度、つまり、もち米が少し白っぽく見えるくらいの高さに合わせるのが良いでしょう。これは、普通の白米を炊くときよりもずっと少ない水の量です。水の量をよく調整することで、べちゃっとせず、パラパラとした食感の薬飯を作ることができます。

Step 5
炊飯器の内釜にもち米を入れて、炊飯を開始します。私はもち米を1時間以上十分に浸水させたので、「早炊き」モードで炊飯しました。通常の白米炊飯よりも時間が短縮され、ずっと早く薬飯を完成させることができます。もちろん、お使いの炊飯器に「薬飯」専用のメニューがあれば、その機能を使うのが最も良いでしょう。通常の白米炊飯モードでも問題ありません。炊飯器の様々な機能を活用して、最適なモードを選択してください。

Step 6
炊飯器から炊きあがった薬飯を取り出すと、見た目には色が薄く見えるかもしれません。しかし、心配しないでください!温かいうちに、すぐにヘラなどでかき混ぜてください。長時間そのままにしておくと、底が焦げ付いてしまうことがあるので、全体を均一にかき混ぜながら、蒸らすように冷ますのが良いでしょう。

Step 7
このように、パラパラとしていて、深い色合いの美味しい薬飯が完成しました!完成した薬飯は、広めのトレイやお皿に広げ、粗熱を取ってください。熱すぎると形が崩れてしまうことがあります。

Step 8
薬飯をきれいな形にしたい場合は、様々な製菓用型を活用してみてください。私はフィナンシェ用のシリコン型にもち米をしっかりと押し込んで、形を整えました。しっかりと押し込むことで、形がきれいに仕上がります。

Step 9
型から薬飯をそっと取り出すと、このように美味しそうな薬飯ができあがります。製菓用型や型などを使うのは久しぶりなので、焼き方を忘れてしまったのではないかと少し反省しています。最近は、家庭料理に集中しすぎて、お菓子作りから遠ざかっているようです。反省の意味を込めて、今後はもっとお菓子作りにも挑戦してみようと思います。でも、今日作った薬飯は本当に素晴らしいでしょう?

Step 10
完成した薬飯は、個別に包装して保存したり、ギフトとして渡せるように仕上げます。お餅の包装用のビニール袋に入れ、全体をテープで密封すると、後で食べるときに手間がかかることがあります。そこで私は、片側をパン用の紐で軽く結び、リボンのように仕上げました。このように包装すると、食べる時にほどくのもずっと簡単になります。ギフトとして渡す際も、このように心のこもった包装を気にすると、受け取る側も気持ちが良いですし、たとえ小さなことでも、思いやりが伝わると思います。どうぞ、美味しく召し上がってください!